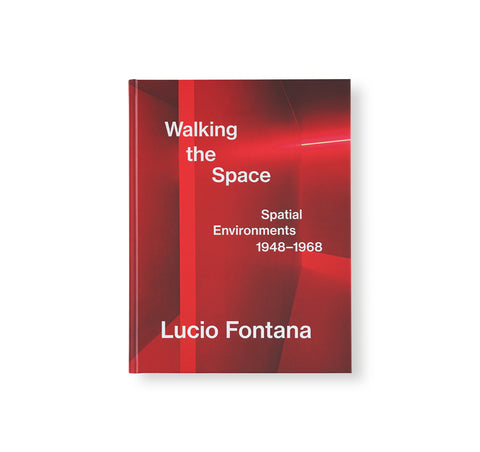MONOCHROME: A DIALOGUE BETWEEN BURRI, FONTANA, KLEIN, MANZONI, & STINGEL
イタリア人画家、彫刻家であるアルベルト・ブッリ(Alberto Burri)、イタリア人アーティストのルーチョ・フォンタナ(Lucio Fontana)、フランス人画家のイヴ・クライン(Yves Klein)、イタリア人アーティスト、ピエロ・マンゾーニ(Piero Manzoni)の作品と、イタリア人アーティストのルドルフ・スティンゲル(Rudolf Stingel)による作品集。2017年にニューヨークの「Nahmad Contemporary」で開催された展覧会に伴い刊行された。既にこの世を去った巨匠らの作品に現代アーティストであるスティンゲルの作品を並べ、単一(モノクローム)の色で制作された絵画を色ごとに展開し、検討する。
モノクロームは抽象絵画の中でも究極の表現であり、絵画を最も純粋な形として凝縮している。その歴史は1900年代に遡り、戦前の旧ソビエト連邦のロシア・アヴァンギャルド芸術家たちと結びつく。第二次世界大戦後は、凄惨な戦争から解放され新たな表現を模索した作家たちによって再びモノクローム表現が復権を得る。戦後のヨーロッパでは、色彩が持つ精神的かつ形而上的な可能性を求めてモノクローム作品が制作される一方、色彩の限界を追い求め、絵画が持つ物質的特徴を強調し、ミニマリズムに繋がっていく表現を追求する作家も現れていた。本書において焦点を当てる作家陣は、1950年代後半から1960年代にかけて、その二律背反を特徴づける作品を生んできた。
本作品群で最も古いモノクローム作品は、モノクローム絵画をはじめとする独特の表現やパフォーマンスで知られる、イヴ・クラインによる「IKB 208」(1957年)。作品の素材や支持体のみに依存しない、芸術の「脱物質化」への探究を象徴している。色彩を認知するために不可欠な空間と光の特性を把握したクラインは、二次元のキャンバスを超え、鑑賞者を三次元的に巻き込む空間性を生み出している。クラインの展覧会に参加したことでも知られるルーチョ・フォンタナは、画面の次元性を再定義し、空間の無限性を強調した。単色のキャンバスに切れ目を入れた「空間概念」シリーズでは、その裂け目で絵画を三次元とし、そこから無限の非物質的空間へと鑑賞者を誘う。フォンタナの弟子であったピエロ・マンゾーニは、フォンタナやクラインと同じ宇宙論的探究を試みながらも、色彩を徹底的に否定した無彩色の絵画シリーズ「Achrome」で単色という概念を解放させる。その作品は、中立性と物理的に削ぎ落としていくことにこだわったミニマリスト的なものであった。アルベルト・ブッリは、フォンタナやクラインと同時代に活動、モノクローム絵画の精神性がもつ特性を超越し、従来用いられてこなかった素材や技法を用いることで絵画の物質性を強調し、その還元主義的な可能性に焦点を当てている。本書では「Combustioni Plastiche (Plastic Combustion)」シリーズを紹介する。ルドルフ・スティンゲルは、先述した作家陣が築いてきたモノクローム作品の持つ多様な歴史を探りながら、現代的な視点で、膨大に存在する表現の中から単色での制作を試みる。物質性へのこだわりを示唆しながら、色の持つ力や時にその不在を利用し鑑賞者を取り巻く空間をも巻き込む。
本作家陣は、空間・知覚・意識を変容させ、あるいは美術品の物理的本質を引き出すことで、色彩が持つ大きな可能性を独自のビジョンで世に示してきた。彼らの「絵画は強力な認識の手段である」という信念が、その後のミニマリズムやコンセプチュアリズム、今日活躍する数多くのアーティストに大きな変化と影響をもたらしてきていると言えよう。
Published on the occasion of the exhibition 'MONOCHROME: A DIALOGUE BETWEEN BURRI, FONTANA, KLEIN, MANZONI, & STINGEL,' May 2 - June 10, 2017. Essay by Francesco Bonami
















![ERWARTUNG by Lucio Fontana [GERMAN EDITION]](http://twelve-books.com/cdn/shop/files/00_c6c54f4c-3735-4a3b-810f-755561d91a41_large.jpg?v=1748403618)